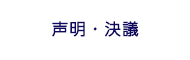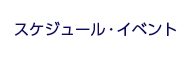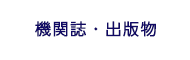解題 「原爆裁判」を現代に活かす!! 編注
日本反核法律家協会 会長
弁護士 大久保 賢一
◆はじめに
被爆80年となる今年、かもがわ出版から「原爆裁判」の資料集が出版された。この資料集には訴状や答弁書はもとより、原告と被告作成の準備書面や証拠の申出書、裁判所の調書、鑑定人作成の鑑定書や鑑定人の証言調書、判決書などが収録されている。裁判に係る書類一切が網羅されているのである。これらの記録は判決書を除き裁判所には存在しない。原告代理人の一人であり日本反核法律家協会の創立者である故松井康浩弁護士のご遺族から日本反核法律家協会が贈呈を受けて、協会の事務所となっている大久保賢一法律事務所に保管されているものがすべてである。これらの資料は日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のたたかいを継承するNPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会に引き継ぐ予定である。
反核法律家協会は、これらの資料をHPにアーカイブとして掲載しているけれど、今回、書籍化されたのである。かもがわ出版から書籍化を提案された時、反核法律家協会の理事会では、書籍化されることによって「原爆裁判」にかかわる資料が一覧できるようになれば協会としてもうれしいけれど、これらの書類をデータ化することは大変だろうとか、需要はあるのかなどという意見も出ていた。そういう心配をよそに、かもがわ出版はその書籍化を進め完成させたのである。反核法律家協会としてもその努力に心から感謝したい。そして、多くの人に活用してもらいたいと祈念している。
◆「原爆裁判」にこだわる理由
「原爆裁判」は1955年4月に提訴され、1963年12月に東京地方裁判所で判決が言渡されている。60年以上も前の、しかも下級審の判決にこだわる意味があるのだろうか。私は大いに意味があると思っている。その理由は、現在、私たちは核兵器が使用される危機の中に生活しており、その状況から脱却するために「原爆裁判」に立ち返る必要があるからである。
「原爆裁判」を提訴した岡本尚一弁護士は次のように語っていた。「この提訴は、今も悲惨な状態のままに置かれている被害者またはその遺族が損害賠償を受けるということだけではなく、この賠償責任が認められることによって、原爆の使用が禁止されるべきである天地の公理を世界の人に印象づけるであろう。この損害賠償訴訟の可能を世界に示すこと自体が世界の平和に寄与することは疑いない」(『原爆民訴或問』)。
このように、「原爆裁判」は被爆者の救済と核兵器の禁止を求める裁判だったのである。それは、核兵器という「究極の暴力」に対して「法という理性」が挑戦した最初のケースなのである。そして、法が核兵器に挑戦する最後のケースになるかもしれないのである。今度、核兵器が使用されれば、人類社会は滅びてしまうかもしれないので、誰も裁判など起こすことができなくなるからである。そのことを念頭に置きながら「原爆裁判」からのメッセージを追体験することにしたい。
◆迫りくる核戦争の危機
前提として、現在、私たちは核兵器使用の危機に直面していることを確認しておく。
国際情勢をよく知る立場にあるグテーレス国連事務総長は「冷戦終結後で、もっとも危険な状況だ。核兵器が使用されなかったのは運がよかっただけだ。」と言っている。核兵器の威力をよく知っている米国の科学者たちは、1947年以降でもっとも危険が迫っており、終末まで89秒としている。そして、ノーベル委員会は、日本被団協は「核のタブー」を形成してきたけれど、そのタブーが破られそうになっているので、日本被団協に平和賞を授与している。さらに、忘れてならないことは、日本政府も核攻撃があった場合の「国民保護計画」を策定していることである。
このように、核兵器が使用される危険性が指摘され、核兵器が使用されることを前提とした施策がとられているのである。そのことを自覚しておきたい。
◆核兵器使用がもたらす事態
核兵器が使用されれば、私たちに何が起きるのであろうか。そのことも確認しておこう。
原爆の父といわれるオッペンハイマーは、核実験の成功に際して「我は死なり、世界の破壊者なり」と呟いた。被爆者は「原爆は人間として死ぬことも、人間らしく生きることも許さない、絶滅だけを目的とした絶対悪の兵器」だとしている(『21世紀 被爆者宣言―核兵器も戦争もない世界を』)。核兵器は「死神」であり「絶対悪の兵器」なのである。
米国、ロシア、イギリス、フランス、中国などの5大核兵器国も加盟する核兵器不拡散条約(NPT)は、核戦争は全人類に惨害をもたらすことになるので、このような戦争を避けるためにあらゆる努力を払うとしている。だから、NPT6条は、核軍拡競争の停止、核軍縮だけではなく、全面軍縮を規定しているのである。また、核兵器禁止条約は、核兵器使用は「壊滅的人道上の結末」が生ずるので、いかなる場合にも再び使用されないようにするには、核兵器を廃絶することだとしている。
そして、5大核兵器国の首脳たちも「核戦争は戦ってはならない。核戦争に勝者はない。」としていることもよく知られていることである。かつて、オバマ元米国大統領は「核なき世界」を口にしてノーベル平和賞を受賞しているし、岸田文雄元首相も「核なき世界」の実現はライフワークとしているところでもある。
要するに、多くの人は、核兵器が使用されれば人類社会が終わるかもしれないので、核兵器は廃絶されるべきものと考えているのである。核兵器が使用されてはならないことは、岡本弁護士が夙に指摘していたように「天地の公理」なのである。
◆危機の現状
にもかかわらず、核兵器使用の危機が迫っているのである。世界には核兵器が12000発以上存在するだけではなく、そのうち数千発はいつでも発射できる態勢にあるといわれている。使用してはならない核兵器が、息を顰め牙を剥き爪を研ぎながら待機しているのである。それらが、意図的だけではなく、事故や故障で発射される危険が指摘されている。発射されたミサイルを呼び戻す方法はない。これらの危険を避けるための唯一の確かな方法は核兵器を廃絶することであるが、核兵器国はその保有に固執している。
そして、プーチン・ロシア大統領やトランプ・米国大統領のような人が「核のボタン」を握っているのである。プーチン大統領は「ロシアのない世界など考えられない。」としているし、トランプ大統領は「なぜ核兵器を使用してはならないのか。」と何回も聞き返す人である。そして、何をしでかすか分からない人でもある。彼らは、世界の核兵器の80%以上を保有している国の軍事と政治の責任者なのである。こうして、私たちは、彼らのような人に、その命運を握られているのである。しかも、日本の歴代首相たちはその米国の核に依存するとしているのである。
加えて、世界には433基の原発が稼働している。原発事故が私たちに何をもたらすかは、私たちが現在目の当たりにしているところである。私たちは、いつ空から死が落ちてくるか分からない「核の地雷原」で生活していることを忘れてはならない。(以下、原発のことは触れない。)
◆「死神」への依存からの脱出のために
けれども、核兵器に依存する彼らは核兵器を「すぐになくそう」とは言わない。核兵器は自国の安全を保障するために必要不可欠だという理由である。自国に攻撃を仕掛ければ核兵器で反撃されて大きな損失をこうむることになるぞと脅して、攻撃を手控えさせるというのである。核兵器は「戦闘の手段」ではなく「秩序を維持する道具」だと位置づけられている。こうして、核兵器は自国の安全を保障し、ひいては自国民の命や財産を守る道具だという理屈で存続することになる。そして、核兵器を禁止しその廃絶を展望する核兵器禁止条約は敵視されるのである。
このように、私たちは、核兵器という「死神」であり「絶対悪の兵器」に依存する政治勢力によって、核戦争の危機にさらされているのである。そういう中で、「原爆裁判」は私たちに何を提供しているのであろうか、また、私たちに、何を宿題としているのであろうか。これらのことをこの資料集からくみ取って欲しいと思う。
◆「原爆裁判」とは何であったのか
「原爆裁判」とは、被爆者が、1955年に、米国の原爆投下は国際法に違反するので、その受けた損害の賠償を日本政府に請求した裁判である。被爆後10年がたっていたけれど、被爆者に対する援護策は何もとられていなかったのである。その裁判を項目ごとに確認していくことにする。
<「原爆裁判」の原告たち>
「原爆裁判」の原告は、配偶者や子どもや両親を亡くしたり、自身もケロイドや病気に苦しめられていた被爆者5名である。訴状では、それぞれどのような被害を受けたのかが描写されている。現代の裁判では、原告本人の言葉で綴られた「陳述書」や法廷での「証言」の機会はあるけれど、「原爆裁判」では原告本人の被害状況についての立証活動は行われていない。訴状の行間から原告たちの被害の状況を推察して欲しいと思う。
もちろん、原爆被爆者は5名に限られたわけではない。厚生労働省によれば、被爆者(被爆者健康手帳所持者)の数は、2022年3月31日現在で、11万8935人とされている。この数は、被爆者として申請して健康手帳の交付を受けた人たちであるので、爆死した人や申請できなかった人や申請しなかった人の数は含まれていない。にもかかわらず、被爆後77年を経過した時点でも11万人を超える「被爆者」が存在しているのである。
だから、「集団訴訟」という作戦も考えられたではないかとの意見もあるかもしれない。けれども、当時の状況からして、原告は5人だけだったのである。岡本弁護士が「原爆裁判」を提起した1953年当時、現在みられるような原水禁運動や被爆者運動は誕生していなかった。これらの運動と組織が発足するのは、1954年のビキニ水爆実験の後なのである。
<原告代理人>
原告代理人は岡本尚一弁護士と松井康浩弁護士である。訴状にはそれ以外の弁護士の氏名もあるし、裁判所の調書にはそれ以外の弁護士が出席した記録もある。けれども、現実に裁判を担ったのはこの二人だけである。
とりわけ、岡本弁護士の情熱は凄かった。法的構成についての研究をし、内外の弁護士たちに協力を呼び掛け、1954年には原爆損害求償同盟を立ち上げている。エピソード的に記しておくと、岡本弁護士はその組織のために30万円の寄付をしている。1954年当時の日本人の平均年間給与所得は年額20万4900円(国税庁『令和2年分 民間給与実態統計調査)と対比して欲しい。岡本弁護士は「原爆裁判」に心血を注いだのである。彼を駆り立てたのは「東京裁判」において原爆投下に対して反省がなかったこと、原爆被害があまりにも凄惨であること、このままでは人類の未来が危ういとの想いだったのである。
その岡本の思いを正面から受け止めたのが松井康浩弁護士である。提訴当時、岡本弁護士は63歳、松井弁護士は33歳である。いわば親子ほどの齢の差である。ちなみに、岡本の息子岡本拓さん(訟務検事もしていた)と松井弁護士は司法研修所の同期だという。岡本弁護士は提訴から3年で他界しているので、その後の5年間は松井弁護士が一人で奮闘することになる。
<原告の請求>
原告が訴えたことは次のようなことである。
原爆は人類の想像を絶した残虐な兵器である。米国の原爆投下は、戦闘員・非戦闘員たるを問わず無差別に殺傷した。原爆投下は国際法と相容れない違法な行為である。原告には米国に対する損害賠償請求権がある。対日平和条約によって、その請求権を放棄した日本政府は、原告に賠償しなければならない。
訴状を読んで改めて感ずることは、ほとばしる情熱と丁寧な論理構成である。私には、到底このような訴状を作成することはできないであろう。このような訴状を作成した先人に心からの敬意を表したい。読者にもぜひ熟読玩味して欲しい。
<被告の対応>
これに対して被告国は、原爆投下は違法ではない。むしろ、戦争終結を早めて多くの人命を救った。賠償請求権などありえないとして徹底的に争った。その応酬を答弁書や準備書面から読み取って欲しい。とりわけ、被告国は、原爆投下直後は、原爆投下を国際法違反としていたにもかかわらず、裁判では国際法違反とは言わなくなったことと、原爆投下は戦争被害を減少させたかのように主張していることに注目して欲しい。被告国は、米国の原爆投下を正当化していたのである。
その背景には当時の国策がある。すでに、政府は1951年に締結されたサンフランシスコ講和条約と旧日米安保条約において、米国の核とドルの傘に依存するという国策を確立していたのである。そして、この国策は現代にいたるも全く変更されていないどころか「日米(核)同盟」として強化されているのである。
<裁判所の判断>
1963年12月7日、古関敏正裁判長、NHK朝ドラ「虎に翼」の主人公のモデル三淵嘉子裁判官、高桑昭裁判官による判決は、原告の請求を棄却した。原告には、国際法上も国内法上も、米国に対しても日本に対しても、損害賠償請求権はないとしたのである。原告や原告代理人の思いは届かなかったのである。けれども、その理由の中で注目すべき二つの判断が示されたのである。
一つは、「原爆は、その破壊力、殺傷力において従来のあらゆる兵器と異なる特質を有するものであり、まさに残虐な兵器である。」としたうえで「米軍による広島・長崎への原爆投下は、国際法が要求する軍事目標主義に違反する。かつ、不必要な苦痛を与えてはならないとの国際法に違反する。」としたことである。
この判断は、資料集に収録されている三人の国際法学者(高野雄一、田畑茂二郎、安井郁)の鑑定意見や安井郁証言を踏まえてのものであった。三人の国際法学者は、表現の違いはあるけれど、誰も原爆投下を適法とはしていないことを資料集で確認して欲しい。
このような丁寧な審理が、下級審の判断でありながら、米国の学者や国際司法裁判所の判事に影響を与えたのである。例えば、1996年、国際司法裁判所は国連総会の「核兵器の威嚇または使用は、いかなる状況においても国際法に違反するか。」という照会に対して「一般的に国際法に違反する。ただし、国家存亡の危機の場合には、合法とも違法とも判断できない。」との勧告的意見を発出しているが、この結論に「いかなる場合も違反する。」として反対したウィラマントリー判事は次のように言っている。「この事件はそもそもの初めより裁判所の歴史にも例を見ない世界的な関心の的になる問題であった。下田事件(原爆裁判のこと)で日本の裁判所に考察されたことはあるが、この問題に関する国際的な司法による考察はなされていない」。このように、「原爆裁判」は国際司法裁判所において参照されていたのである。
<「原爆裁判」と国際司法裁判所の判断枠組み>
ところで、「原爆裁判」判決は、原爆は人間に何をもたらしたのかという事実を認定した上で、それを原爆投下時の国際法(国際人道法・戦争法、戦闘においても禁止される方法手段を規制する法)に照らして違法という判断をしている。裁判とは、法を大前提とし事実を小前提として判断を下すという三段論法であるが、「原爆裁判」も勧告的意見も原爆が人間に何をもたらしたのかを認定したうえで国際法に照らして違法という判断を下しているのである。この両者の判断枠組みは共通なのである。
「原爆裁判」において、原告は「被爆の実相」を基礎において主張し、裁判官たちは、被告国の原爆投下擁護の主張に引きずられずに、原爆の特性を丁寧に認定し、国際法学者の鑑定結果を踏まえて、国際人道法違反を導き出していることを資料から確認していただきたい。当時の国際人道法(戦争法)が丁寧に検討されていることに気が付くであろう。
<「人道アプローチ」との関係>
そして、この「核兵器は人間に何をもたらすか」という事実に着目して核兵器の具体的危険性を問題にする潮流は「人道アプローチ」あるいは「人道イニシアチブ」といわれている。この潮流は「核兵器は国家安全保障のために必要で有用だ」という抽象的議論を克服して、核兵器禁止条約の誕生と普遍化に大きな役割を果たしている。
この潮流は核抑止という「神学論争」を現実の国際法の俎上にのせ、それを解体し、2025年に開催された核兵器禁止条約第3回締約国会議において「核抑止力は、すべての人の生存を脅かす核リスクの存在を前提にしている。意図的であれ偶発的であれ、核兵器の使用は壊滅的な人道的結果をもたらす。」との結論を導き出しているのである。
現代の国際社会においては、いかなる核兵器の使用も武力行使の手段や方法は無制限ではないとする国際人道法に違反するのでその廃絶をしなければならないという規範が形成されつつあることを確認しておきたい。
1963年の「原爆裁判」は、1996年の勧告的意見を経由して、2021年に発効した核兵器禁止条約へと継承されているのである。「原爆裁判」は「核兵器のない世界」を創るための国際人道法の分野でのまさに「事始め」の役割を果たしているのである。
<被爆者援護との関係>
もう一つは、判決が「戦争災害に対しては当然に結果責任に基づく国家補償の問題が生ずる。国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのだから、十分な救済策を執るべきである。戦後十数年を経て、高度成長をとげたわが国においてこれが不可能であるとは考えられない。本件訴訟を見るにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられない。」としたことである。
判決は、被爆者に対して十分な援護の措置をとらない政治の責任を指摘したのである。戦争被害者の救済策をとる第一次的責任は政治にあることはそのとおりであるが、裁判所はその「政治の貧困」を嘆けば足りるということでもないであろう。原告の請求を認容するという選択肢もあるからである。安井郁鑑定人は「鑑定事項ではないが」と断りながら、憲法29条3項(私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。)に依拠しての補償の可能性を証言していることに留意しておきたい。
<裁判官の勇気>
それはそうであるが、私はこの判決を非常に勇気あるものと評価している。米国の原爆投下を国際法上違法と断言し、政府や国会の怠慢を指摘することなどはそれなりの覚悟がなければできないであろうと思うからである。なぜ、そのような判決が可能だったのであろうか。私は、三人の裁判官たちは、司法に携わる者として、原爆という「残虐な兵器」がもたらした「被爆の実相」を無視することはできなかったからだろうと推察している。法の根底にあるのは人道と正義である。法に携わる者として「原爆がもたらした事実」を「法は容認する」などとはできなかったのであろう。
そして、もう一つ指摘しておきたいことは、当時の裁判所にはこのような判決が書ける雰囲気があったということである。この裁判の口頭弁論手続きに唯一人全過程に携わった三淵嘉子裁判官の夫である三淵乾太郎氏の父は三淵忠彦初代最高裁長官である。三淵長官はその就任挨拶(「国民諸君への挨拶」)で次のように言っていた。「裁判所は、国民の権利を擁護し、防衛し、正義と衡平を実現するところであって、圧制政府の手先となって国民を弾圧し、迫害するところではない。裁判所は真実に国民の裁判所になりきらなければならぬ」。気高い決意表明といえよう。司法反動の嵐の絶頂期よりは前の時代だったのである(「砂川事件」の差戻し審の有罪判決について、最高裁が上告を棄却するのは奇しくも1963年12月7日)。
◆被爆者援護政策への影響
日本の政治は、原爆裁判を受けて、被爆者援護のための法制度を整備した。けれども、現状が十分であるとは到底いえない状況にある。被爆者にとどまらず、戦争被害者の救済という観点からしても「政治の貧困」は解消されていない。その理由は「原爆裁判」が指摘した「結果責任に基づく国家補償」を棚上げしていることにある。政府は「戦争による被害は国民ひとしく受忍すべきである」(受忍論)として補償責任を果たすことを拒否しているのである。
それが、ノーベル平和賞受賞記念式典で、田中熙巳被団協代表委員が「何十万人という死者に対する補償はまったくなく、日本政府は一貫して国家補償を拒み、放射線被害に限定した対策のみを今日まで続けております。もう一度繰り返します、原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府はまったくしていないという事実をお知りいただきたい。」と演説した背景事情である。
原爆被害者援護でも、また戦争被害者援護でも、この国の「政治の貧困」は改善されていない。政府の無責任な態度はそのままなのである。被爆80年は戦後80年でもある。政府は戦争被害者が死に絶えるのを待ちながら「新たな戦前」を準備しているかのようである。「戦争による結果責任」に無頓着な者が「新たな戦争」を準備しているのである。今、この国は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きる」事態にあることを自覚しておきたい。
◆核抑止論の克服
このように、「原爆裁判」は核兵器廃絶という課題でも被爆者援護という課題でも大きな役割を果たしている。けれども、核兵器はなくなっていないだけではなく核兵器使用の危険性がかつてなく高まっていることは冒頭に述べたとおりである。また、被爆者援護の課題でも、私たちに課されている宿題は多いのである。そこで、最後に、核兵器は私たちの安全を保障するものだという核抑止論について述べておくことにする。核抑止論こそが「核兵器のない世界」の実現を遠ざけ、核兵器使用の危険性を極大化している元凶だからである。
<核抑止論の原型>
核抑止論の原型を紹介しておく。バーナード・ブロディ―(Bernard Brodie、1910年~1978年。米国の国際政治学者)の1946年の論稿である(戸崎洋史『核戦略の動向と核軍縮管理への含意』・『軍事研究』電子版14巻1号2025年3月による)。
原爆時代の米国の安全保障計画における最初の、そして最も死活的なステップは、攻撃された場合に同様の報復の可能性を保証する措置をとることである。このように述べる筆者は、原爆が使用される次の戦争でどちらが勝つかについて、ひとまず関心がない。これまで、我が国の軍事組織の最大の目的は戦争に勝利することであった。これからは、戦争を回避することが最大の目的でなければならない。それ以外の有益な目的は、ほぼありえない。
このブロディーの議論の特徴は「原爆は戦争の在り方を変えた」ということと「敵の攻撃と同程度の報復を可能とする軍事力が必要」という二つである。一つ目の特徴は、原爆時代になったので、それが使用される戦争では「どちらが勝つか」は言えない。だから、軍事組織の目的は「戦争に勝つ」ことではなく「戦争を回避する」ことになるとされている。二つ目は「報復の可能性を保証するための措置」としての軍事力が必要とされていることである。「戦争を回避する」だけではなく「報復が可能な軍事力」の確保が提唱されており、核攻撃には核攻撃で報復することになるのである。
要するに、核攻撃に対する反撃を準備しながら「戦争を回避する」というのである。
ここに、核兵器によって仮想敵国の攻撃を抑止し、自国の安全を確保するという現代の核抑止戦略(核抑止論)の原型を見て取ることができる。
結局、この理論は「戦争を回避する」としながら「戦争に備える」という矛盾を内包しているのである。そして「報復のための軍事力」が必要とされているので「戦争の廃止」は論外となるのである。こうして、この理論では「戦争がもたらす危険」からは解放されないし、核戦争も例外とはされていないので「核戦争がもたらす危険」からも免れることはできないのである。だから、この理論では「核なき世界」はいつまでも実現しないことになる。オバマ元米国大統領が「私が生きている間には無理かもしれない」と言ったのはそういうことである。
こうして「戦争を回避する」としながら戦争の危険から免れることができないという矛盾は解消されないままに現在に至り、核戦争の危機が迫っているのである。
<1946年という時代>
ところで、このブロディーの論稿は1946年である。原爆投下1年という時期に、このように核兵器の必要性を説く議論が提起されていたことは驚きである。他方1946年1月24日の国連第1回総会第1号決議は、国際原子力委員会の設置と核兵器および大量破壊が可能なすべての兵器の廃絶を目指すとしている。さらに、同年12月14日に国連総会で採択された「軍縮大憲章」(「軍備の全般的な規制及び縮小を律する原則」)は、「原子力兵器及び現在と将来に大量破壊兵器に応用できる他の一切の主要な兵器を禁止」するという「緊急の目的」のために「必要な手段」をとるとしていた。このように、一方では核兵器に依存するための「理論」が提起されていたが、国連総会は核兵器の禁止や廃絶を決議していたのである。そこには明確な対立があったのである。
◆現在の課題
その対立は現在も続いている。核兵器はその存在そのものが危険なので廃棄しようという潮流と核兵器に依存して戦争を回避し安全を確保するという潮流との対立である。それは、核兵器廃絶を「喫緊の課題」とする潮流とそれを「究極的課題」であり今すぐなくすことを拒否するという潮流の対立である。そして、核兵器国では「今はなくさない」とする勢力が政治権力を握っているので、核兵器が廃絶される具体的展望は見えていない。
ところで、核兵器に依存する勢力が政治権力を握ることができるのは「核兵器がないと国家の安全が危うくなる」という不安の掻き立てが国民をとらえているからである。そうすると、核兵器の廃絶を急ごうとすれば、そのような不安を解消するための理論と運動の構築が求められることになる。
◆「平和を愛する諸国民の公正と信義」という選択肢
私は、戦争の恐怖から免れて安全な生活を送るためには「戦争を回避」するだけではなく「戦争を廃止」する必要があると考えている。そのためには、日本国憲法がいうように「一切の戦力の放棄」がベストの選択である。戦力がなければ戦争はできないからである。それは「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの生存と安全を保持すること」を意味している。
このような発想は、自民党などからは「ユードア思想」だと非難されているけれど、それは決して「ユートピア思想」ではない。世界には核兵器どころか、軍隊のない国が26ヵ国存在しているからである(国連加盟国は193ヵ国)。核兵器や戦力がなくても国家は存在しうるのである。
加えて、自衛のためであれ、正義の実現のためであれ、武力の行使が許容されれば「絶対悪の兵器」である核兵器に依存することになる。それは、1955年の「ラッセル・アインシュタイン宣言」が指摘するだけではなく、現実の国際政治を見れば明らかであろう。
核兵器が存在する限り、核兵器が使用され「壊滅的人道上の結末」という「みんな死んでしまう危険」から解放されることはない。それを避けるためには、核兵器に依存する戦略を放棄しなければならない。人間が作ったもので人間が滅びるという馬鹿げた事態は避けなければならないからである。こうして、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの生存と安全を保持する」という選択肢が浮上してくるのである。
核兵器という「死神」や「絶対悪の兵器」に依存するのではなく「平和を愛する諸国民の公正と信義」に依存するという選択である。大分岐がここにある。
◆まとめ
「原爆裁判」判決は「人類の歴史始まって以来の大規模、かつ破壊力を持つ原爆の投下によって損害を被った国民に対して、心からの同情の念を抱かないものはいないであろう。戦争を全く廃止するか少なくとも最少限に制限し、それによる惨禍を最少限にとどめることは、人類共通の希望であり、そのためにわれわれ人類は日夜努力を重ねているのである。」としていた。
けれども、判決当時、日本国憲法は戦争だけではなく一切の戦力も交戦権も放棄していたのである。その理由について、憲法が公布された1946年11月、当時の政府は「原子爆弾の出現は、戦争の可能性を拡大するか、または逆に戦争の原因を終息せしめるかの重大な段階に達した。文明が戦争を抹殺しなければ、やがて戦争が文明を滅ぼしてしまう。ここに、9条の有する重大な積極的意義がある。」としていたのである。
日本国憲法は「核のホロコースト」の上に成立していたのである。裁判官たちはそのことには触れてはいない。私はこの部分はもう少し工夫して欲しかったと思っている。けれども、原爆投下による被害が「人類の歴史始まって以来の規模」であったことや「戦争を全くなくすことが人類共通の希望」であることはそのとおりである。
その想いは、田中熙巳演説の「人類が核兵器で自滅することのないように!!核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて共に頑張りましょう!!」という結びの部分と共鳴している。まさに、核兵器の廃絶のみならず、戦争の廃絶は「人類共通の希望」なのである。
私は、憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの生存と安全を保持しようと決意し」ている徹底した非軍事平和主義を踏まえながら、「原爆裁判」の現代的意義を再確認し、核兵器も戦争もない世界を創造することが「原爆裁判」からの私たちへの宿題だと受け止めている。
この資料集は、核兵器も戦争もない世界を展望するうえで「原爆裁判」という貴重な資源を提供してくれるであろう。被爆80年に際して、この資料集が発刊されたことを歓迎し、大いに活用したいと思っている。
【編注】 本稿は、2025年7月にかもがわ出版より刊行された『「原爆裁判」全資料』(日本反核法律家協会監修)所収の解題を、機関誌『反核法律家』№124(2025年秋号)に許可を得て掲載したものを転載した。