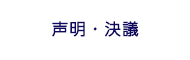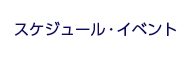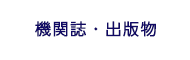はじめに
埼玉弁護士会は、10月2日、「自衛隊を憲法に明記する憲法改正に反対する決議」を採択した。安倍首相が進めている憲法9条1項と2項はそのままにして、実力組織としての自衛隊の保持を憲法に書き加えようという「自衛隊明記案」に反対することを、会の総意としたのである。
まだ、発議されているわけでも、憲法審査会に提案されているわけでもない「自衛隊明記案」について、慎重審議を求めるのではなく、反対の意思を表明したのである。
もともと、埼玉弁護士会は、2008年5月に「日本国憲法の平和主義を堅持することを求める決議」を採択していた。「当会は、憲法9条2項の非軍事平和主義の規範が堅持されることを求め、21世紀を『全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利』が保障される平和と人権の世紀にするための諸活動に取り組む」というものであった。
今回の反対決議は、それから10年を経た現在の状況を踏まえての意見表明である。
採択までの手続き
現在、埼玉弁護士会の会員は860人。もちろん、憲法についての関心の濃淡、改憲についての賛否、弁護士会の在り方などについて多様な意見が存在している。その中で、会としての意見をまとめていくということは簡単なんことではない。だから、現在の改憲論議に危うさを覚えている執行部は、できるだけ大勢の会員に関心を持ってもらい、そのうえで会内合意を形成することに腐心していた。登録後数年という白神優理子弁護士を招いての学習会や、支部ごとの意見交換会なども開いてきた。その中で、「国民投票前の意見表明は政治色が強く、時期尚早」、「弁護士会内で反対意見は軽々に言えない。貝になりたい思いがする」、「国防関係の議論について、弁護士個人の思想信条を制約することにならないか」、「改憲にネガティブな印象を与えるべきではない」などの反対意見も出されるようになった。
総会の様子
臨時総会には、97人が参加して(委任状出席も含めれば265人を超える)、熱心な討論が行われた。決議に賛成する意見が多数であったけれど、反対意見ももちろん表明されていた。その中で、傾聴すべきと思ったのは「安保関連法案のように、憲法に照らして違憲だから反対するという議論と、憲法改正についての賛否は次元が異なる問題である。そもそも、そのような事柄は、憲法改正権力者である国民に委ねられるべきである」という意見である。安保法制は違憲であるとして共同していた人たちの中にも見受けられる議論である。国民がそれを選択するならそれも民主主義であってやむを得ない、という立場である。
この意見が述べられた直後、ある会員が「私の妻の母は被爆者である。健康状態はすぐれないままである。この改憲が行われ、自衛隊が書き込まれることになったら、被爆者たちにどのように説明するのか」と発言していた。大日本帝国の侵略や植民地支配の行き着いた先が原爆投下であったことに思いを致すとき、その発言には強い共感を覚えたものであった。
憲法9条改正の限界
決議に次のような一文がある。「自衛隊明記案は日本国憲法の恒久平和主義と抵触し改正限界を超えるものとして許されない」というのである。この論理によれば、自衛隊明記案についての議論は、単に政治的というだけではなく、憲法論として取り扱う必要が出てくるのである。9条改正については、1項も2項も改廃できるとする無限界説、1項の改廃は限界を超えるが2項の改廃は超えないという説、2項の改廃も限界を超えるとする説がある(註解日本国憲法上・251頁)。埼玉弁護士会は、その最後の説に立っているのである。2008年の決議ではこの議論は行われていなかった。改憲にかかわる議論を政治論にとどめないで、法律論として議論するためには、このような論点設定も求められているのである。非軍事平和主義に基づく戦力の放棄と交戦権の否認は、憲法改正の限界を超えるとする議論を深める必要があるといえよう。
核の時代における平和主義の在り方
決議は9条2項の意義について次のように述べている。「日本国憲法の恒久平和主義、なかでも9条2項の戦力不保持規定は、不戦条約や国連憲章をさらに推し進めた規範であり、それは、人類滅亡に直結する核兵器の出現を受けた現代における国際紛争の指針として極めて先駆的であり、普遍的意義を有する」というのである。この背景にあるのは「人類は核兵器を持ってしまった。核兵器を使用しての武力の行使が行われれば、戦争が文明を滅ぼすことになる。武力での紛争解決が禁止されるのであれば、戦力を持つ必要はない」という発想と論理である。1946年当時の制憲議会で政府が展開していた論理であり、樋口陽一先生が「8月6日と9日という日付を挟んだ後の日本国憲法にとっては、「正しい戦争」遂行する武力によって確保する平和という考えは受け入れることはできなくなった」としているところでもある。
小括
賛成253、反対10で採択されたこの決議の特色は、自衛隊を明記する改憲を9条2項の平和主義の限界を超えているとしていることと、その根拠を、核の時代における憲法9条2項の先駆性と普遍性に求めていることにある。私は、先に紹介した被爆者に対してどのように説明するのかという発言は、核の時代における平和主義の在り方を端的に表現しているものだと思う。そして、専守防衛などとして自衛隊を認める議論についての危うさを危惧せざるを得ないのである。
いかなる事情であれ、核兵器が使用されれば、壊滅的な人道上の結末を迎えることになることは、核兵器禁止条約で確認されているところである。そして、終末時計は人類滅亡までに残された時間は2分だとしている。私たちは、いまだ核兵器が15000発も存在し、そのうちの数千発が発射可能状態に置かれていることは忘れないようにして、平和主義の在り方を考えなければならないのである。