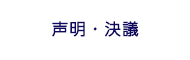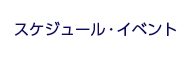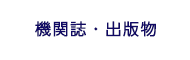核兵器を必要とする人たちとどう向き合うか
―バーナード・ブロディーの言説をヒントにして―
日本反核法律家協会 会長
弁護士 大久保 賢一
◆迫りくる核兵器使用の危機
世界には約1万2500発の核兵器が存在し、その内約4000発は配備されています(※1)。配備されているということは、使用できる状態にあるということです。その核兵器は意図的でなくても発射される可能性はあります。現に、そういう事故は起きています(※2)。
ウクライナを侵略しているロシアのプーチン大統領は、ロシアが危なくなれば核兵器を使用すると公言しています。世界情勢をよく知るグテーレス国連事務総長は核兵器使用の危険が冷戦終結後で最も高まっていると警告しています。日本被団協にノーベル平和賞を授与したノーベル委員会は「核のタブー」が脅かされているとしています。「終末時計」は89秒とされています(※3)。核兵器使用の危機が迫っているのです(※4)。
核兵器が使用されれば「全人類に惨害」(核不拡散条約)や「壊滅的人道上の結末」(核兵器禁止条約)が起きることになります。要するに、人類社会が消滅するかもしれないのです。だから、核兵器国の首脳もG7の指導者も核兵器を使用してはならないとしているのです。核兵器使用禁止は「世界の公理」といえるでしょう。にもかかわらず、核兵器使用の危険性が高まっているのです。
この危険性を根本的に解消する方法は核兵器をなくすことですが、核兵器国はなくそうとはしていません。核兵器を禁止し、核兵器をなくそうとする核兵器禁止条約は発効していますが、日本含む核兵器に依存する国はこの条約を敵視しているからです。その理由は「核兵器によって自国の安全を確保する」という戦略にあります。要するに「核兵器は必要」としているのです。核兵器国が核兵器を廃棄しない限り「核兵器のない世界」は実現しません。こうして、人類社会を消滅させる力を持つ核兵器は温存されているのです。
このように、私たちは、いつ、空から死が落ちてくるかわからない世界(※5)で日常生活を送っているのです。まず、そのことを自覚しておきましょう。
そこで、ここでは、戸崎洋史広島大学平和センター准教授の『核戦略の動向と核軍縮管理への含意』(※6)が紹介しているバーナード・ブロディーの言説を手かがりとしながら、「核兵器は必要」としている人の意見を検討してみることにします(※7)。
なお、核戦略とは国家安全保障のために核兵器をどのように活用するかという戦略ですし、核軍縮管理とは核兵器の存在を前提としていますから、核兵器を廃絶するという考えとは全く異なる思考方法です(※8)。以下は、そのことを前提として読み進めてください。
◆核戦略の根幹
戸崎氏はバーナード・ブロディー(Bernard Brodie、1910年~1978年。米国の国際政治学者、軍事戦略家)の1946年の論稿(※9)を引用しています(※10)。
原爆時代の米国の安全保障計画における最初の、そして最も死活的なステップは、攻撃された場合に同様の報復の可能性を保証する措置をとることである。このように述べる筆者は、原爆が使用される次の戦争でどちらが勝つかについて、ひとまず関心がない。これまで、我が国の軍事組織の最大の目的は戦争に勝利することであった。これからは、戦争を回避することが最大の目的でなければならない。それ以外の有益な目的は、ほぼありえない。
戸崎氏は、ブロディーのこの言説を「核戦争、さらには核戦争にエスカレートしかねない戦争自体の抑止を最優先の目標に据えた、現在にも通底する核戦略の根幹を喝破した。」と評価しています。戸崎氏は「核戦略の根幹」は「戦争の抑止」としているのです。
ブロディーは、原爆時代であることを前提に、攻撃と同程度の報復の保証の必要性を説いていますが、軍事組織の目的を「戦争に勝利すること」ではなく「戦争を回避すること」にしているので、核兵器を「戦争の抑止」の手段とする現在の核戦略に通底しているとの評価に異議はありません。この「核兵器を戦争の抑止の手段とする」という言説は、核抑止論といわれる現代の核戦略の根幹をなしているのです。
◆ブロディーの議論の特徴
ブロディーの議論から見て取れるのは「原爆は戦争の在り方を変えた」という認識と「敵の攻撃と同程度の報復を可能とする軍事力が必要」という二つの特徴です。
一つ目の特徴は、原爆時代になったので、それが使用される戦争では「どちらが勝つか」は言えない。だから、軍組織の目的は「戦争に勝つ」ことではなく「戦争を回避する」ことになるとされているのです。ここには「核戦争を戦ってはならない。核戦争に勝者はない。」という発想の原点を見て取ることができます。彼もより安全な世界を求めて「軍の役割」の変化を主張しているのです。そこに着目すれば「反戦思想」が含まれているのです。
二つ目は、「報復の可能性を保証するための措置」としての軍事力が必要とされていることです。そういう意味では「非軍事思想」の対極にあるのです。「戦争を回避する」だけではなく「報復が可能な軍事力」の確保が提唱されているのです。核攻撃には核攻撃で報復することになるのです。このように、この思考には、原爆に対抗するための原爆、水爆に対抗するための水爆、それらを運搬するための道具や技術の開発という際限のない軍拡競争が組み込まれているのです。
結局、ブロディーは、戦争を回避するとしながら軍拡競争を提唱しているのです。ここに、核兵器によって仮想敵国の攻撃を抑止し、自国の安全を確保するという現代の核抑止戦略(核抑止論)の原点があるのです。彼は核抑止論の「元祖」といえるでしょう。
◆ブロディーの発想の背景と矛盾
ブロディーの発想の背景には、原子爆弾が戦争の性質を変えたことにあります。ブロディーも原爆を「絶対兵器」(The Absolute Weapon)としていたようです。彼は、被爆者が「核兵器と人間は共存できない」としていることは知らなかったでしょうが(知っていても無視するでしょうが)、原爆を開発したオッペンハイマーが「我は死なり、世界の破壊者なり」としていたことは知っていたでしょう。そして、彼も原爆の特殊性を理解していたので、戦争を回避する必要性を提案したのでしょう。
もちろん、戦争を回避するという目的に異存はありません。戦争がない方が人々は安全に暮らせるからです。ただし、彼は「戦争の回避」は言いますが「戦争の廃止」は言っていないのです。
彼は「報復のための軍事力」の保持は必要としているのですから「戦争の廃止」は論外となるのです。「戦争を回避」する努力はするけれど同時に「戦争に備える」ことになるのです。だから、結局、この理論では「戦争がもたらす危険」からは解放されないのです。もちろん、核戦争も例外とはされていないので「核戦争がもたらす危険」からも免れることはできないのです。
このように、彼の理論は「反戦思想」を含むように見えますが「報復のための軍事力」が推奨されているので、最終的には核兵器使用も想定されているのです。彼の理論には「戦争を回避する」としながら「戦争に備える」という矛盾が内包されているのです。
彼の議論は、現在、日米両国で共有され、中国の行動を「抑止する」ために「対処力」を強化するという形で活用されています(※11)。中国の行動を抑止するためのミサイルを全国に配備する準備が進められているのです。逆に、中国も日本全土を射程内とするミサイルを所持しています。もちろん、核弾頭を装備することも可能です。「反戦思想」などは完全に消え去り「軍事力の強化」だけが活性化しているのです。
そのことを確認した上で、彼の理論と根幹において共通する「核兵器によって仮想敵国の攻撃を抑止し、自国の安全を確保するという核抑止戦略」の問題点を検討してみましょう。
◆核抑止戦略の問題点
<主観に依存する非合理性>
第一に、この戦略では、相手方の攻撃を抑止するために、自国の「報復能力」を確保するだけではなく、それを相手方に知らしめ、相手方がその行動をとらないようにする必要があります。けれども、そもそも、相手方がどのような発想をし、どのような行動に出るかは相手方が決めることです。だから、自分が考えているとおりに相手方が行動する保証はありません。
このことについて、1980年の国連事務総長報告は「抑止の考え方は超大国の関係の基礎をなしているとはいえ、相手国が戦略理論を受け入れているかどうか、また基本的考え方についての相互の理解が存在しているかどうかについての確実性を持った指摘をすることは困難」としています(※12)。
特に、相手方が「死なばもろとも」と考えた場合には抑止力は機能しないでしょう。このことについて、1955年、ウィンストン・チャーチル元イギリス首相は、「安全は恐怖によって丈夫な子供に育ち、生存と全滅は双子の兄弟となるというのは、人を惹きつけるものがある」が「常軌を逸した者または独裁者が防空壕に追い詰められヒトラーの気分になった場合には当てはまらない」と言ったそうです(※13)。「生存と全滅は双子の兄弟となる」という言い方はチャーチルらしいところでしょう。
また、先に紹介した事務総長報告は「大きなストレスの下で、人間が、前もって決められたとおりに行動するかどうかは、疑問。しばしば間違いがおかされ、突飛な行動がとられる。」としています。
いずれにしても、人は常に合理的に行動するわけではないことは誰でも知っていることですし、体験していることでもあるでしょう。相手の主観に依拠する戦略に客観的合理性はありえません。これがこの戦略の致命的弱点です。
<普遍性の欠落と脆弱性>
第二に、この戦略を全ての国がとったらどうなるのでしょうか。自国の安全保障のために全ての国家が核兵器を持つことを想像してみてください。どんなに危険な国際社会が現れるか誰にでもわかることでしょう。このことについて、1995年7月に広島で開催されたパグウォッシュ会議の声明は「ある国家が核抑止力を獲得したいということは、論理的に突き詰めていけば、全ての国が核抑止力を備える状態が想定され、実際にそうなったら世界は非常に危険な場所になってしまうことであろう。」としています(※14)。
安全を求める戦略がより危険な世界を創ることになるのです。このように、この理論には普遍性がないのです。
その普遍性のなさを糊塗するために、自国は持つけれど他国には持たせないという仕掛けが作られています。「俺は持つお前は持つな核兵器」というNPT体制です。けれども、それは不公平・不平等であるがゆえに、その脆弱性が露見しています。インドやパキスタンそしてイスラエルはNPTに背を向けて核兵器国となっています。北朝鮮は、NPTから脱退して、核兵器を開発しています。
こうして、この戦略は危険で脆弱な世界を形成することになるのです。
<破綻しない保証はない>
第三に、抑止が破綻しないことは誰も保証できません。未来は不確実だからです。抑止が効果を発揮せず、相手国が攻撃をしてきた場合、自国にも報復する力はあるので、双方が破滅することになります。「相互確証破壊」という事態です。自国の安全を確保するための戦略が自国を滅ぼすという「究極のパラドックス」が起きるのです。
このことについて、国際政治学者ハンス・モーゲンソーは次のように言っています。「核軍事力を行使して破壊するぞと相手方を脅すことは、一定の範囲内では合理的でありうる。だが、相手方を実際に破壊することはそれによって自身の破壊をも招くことになるので、非合理的といわなければならない。」(※15)。私は、核抑止論の合理性を一切認めないけれど、抑止の破綻はありうると思うので、彼の結論に説得力を認めています。
<他国を巻き込む>
第四に、その破綻は当事国だけではなく全地球を巻き込むことになります。それが核戦争の特徴です。核戦争の影響を限定することはできません。いかなる国家にも、他国を巻き込んでの破滅をもたらす権限はありません。一部の国の安全保障の推進が、人類文明の消滅をもたらすことなど許されないのです。
このことについて、先に紹介した事務総長報告は「もし仮に、抑止の理論が完全に安定した現象だとしても、この均衡に引き続き依拠することに強い道徳的、政治的反論がある。人類文明の消滅の展望が、一部の国によって自国の安全保障の増進のために利用されるのは許されないことである。」としています。
中立国(※16)や自然環境に悪影響を与える武力の行使は禁止されている(※17)ことも忘れてはなりません。
<危険な集団的誤>
このようにこの戦略は身勝手で危険なものなのです(核抑止論に対する批判はこれに留まるものではありません。主要なことに限定しただけです)。だから、核抑止論は、先に述べてきたように国連において「抑止論はさまざまに仮定された核戦争のシナリオの上に築かれた虚構」、「抑止の過程を通じての世界の平和、安定、均衡の維持という概念は、おそらく存在するもっとも危険な集団的誤謬」などとされているのです(※18)。
この誤謬の原因は「戦争の抑止」を軍事力に求めたことにあります。「戦争を抑止する」という目的のために「戦争を準備する」という手段はもともと矛盾していますから、それがいろいろな形で噴出するのです。
それは、手段が目的の実現にふさわしくないことを意味しています。違う言い方をすれば、目的達成の手段が目的の実現を阻害するだけではなく、目的と反対の結果をもたらすのです。これは道徳や倫理とは別の論理の問題なのです。ブロディーの議論は、そもそも、こういう矛盾を内包していたのです。それは、全人類に破滅をもたらすかもしれない矛盾であり、それが顕在化しないのは「単なる幸運」でしかないのです。
◆1946年という時代
ところで、このブロディーの論稿の発表は1946年です。原爆投下後1年という時期に、このように核兵器の必要性を説く議論が提起されていたのです。
他方1946年1月24日の国連第1回総会議第1号決議は、国際原子力委員会の設置と核兵器および大量破壊が可能な全ての兵器の廃絶を目指すとしていました。このことは核兵器禁止条約の前文でも確認されているところです。更に、1946年12月14日に国連総会で採択された「軍縮大憲章」(軍備の全般的な規制及び縮小を律する原則)は、「原子力兵器及び現在と将来に大量破壊兵器に応用できる他の一切の主要な兵器を禁止」するという「緊急の目的」のために「必要な手段」をとるとしていました。
このように、一方では核兵器に依存するための「理論」が提起されていましたが、国連総会は「核兵器や大量破壊兵器」の禁止や廃絶を決議していたのです。
そこには明確な対立があったのです。
◆現在の課題
その対立は現在も続いています。核兵器に依存して戦争を回避し安全を確保するという潮流と核兵器はその存在そのものが危険なのでそれを廃棄しようという潮流の対立です。核兵器が危険な存在であることには双方に争いはありません。また、核兵器が使用されれば、道義的にも倫理的にも容認できない事態が生ずることは誰も否定していません。だから核兵器をなくすことには誰も反対していないのです。
けれども、核兵器を禁止し廃絶しようとする核兵器禁止条約については厳しい対立があるのです。
核兵器廃絶を喫緊の課題とする潮流とそれは究極的課題であり今すぐなくすことには反対という潮流の対立です。そして、核兵器国では「今はなくさない」とする勢力が政治権力を握っているので、核兵器が廃絶される具体的展望は見えていないのです。
ところで、核兵器に依存する勢力が政治権力を握ることができるのは「核兵器がないと国家の安全が阻害される」という不安の掻き立てが国民をとらえているからです。
そうすると、核兵器の廃絶を急ごうとする私たちの課題は、そのような不安を解消するための理論と運動の構築ということになります。核兵器に依存しない安全保障政策を提案し、それを実現することが求められているのです。そのことを考えてみましょう。
◆平和を愛する諸国民の公正と信義」という選択肢
私は、戦争の恐怖から免れて安全な生活を送るためには「戦争を回避」するだけではなく「戦争を廃止」する必要があると考えています。そのためには、日本国憲法がいうように「一切の戦力」の放棄がベストの選択です。戦力がなければ戦争はできないからです。それは、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの生存と安全を保持する」ことを意味しています。
このような発想は、自民党などからは「ユートピア思想」だと非難されています。けれども、それは決して「ユートピア思想」ではありません。世界には核兵器どころか、軍隊のない国が26ヵ国存在しているからです。核兵器も戦力も、なくても国家は存在しうるのです。自民党の非難は現実を無視しているのです。
加えて、自衛のためであれ、正義の実現のためであれ、武力の行使が許容されれば「絶対的兵器」である核兵器に依存することになります。それは、1955年の『ラッセル・アインシュタイン宣言』が指摘するだけではなく(※19)、現実の国際政治を見れば明らかです。
核兵器に依存する限り核兵器が使用された場合「壊滅的人道上の結末」という「みんな死んでしまう危険」から解放されることはありません。それを避けるためには、核兵器に依存する戦略を放棄しなければならないのです。人間が作ったもので人間が滅びるなどという馬鹿げた事態は避けなければならないからです。
こうして「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの生存と安全を保持する」という選択肢が浮上してくるのです。
核兵器という「絶対兵器」に依存するのではなく「平和を愛する諸国民の公正と信義」に依存するという選択は歴史的必然性を帯びているのです。核兵器の被害に直面した日本が、核兵器を投下した米国の将軍の支配の下で「絶対平和主義」に基づく「平和憲法」を樹立したのは、決して偶然ではなく、核兵器が持つ「死神であり破壊者」である性質を知ったからに他ならないのです。それは「比類のない選択」だったのです(※20)。
◆「公正と信義」を信頼することの必要性と可能性
確かに、「公正と信義」を信頼して「無防備になる」などということは「狂気の沙汰」に思われるでしょう。けれども、直ぐにでも発射できる核兵器の下で日常生活を送ることも「狂気の沙汰」ではないでしょうか。空から死が落ちてくる世界で生活することは「狂気の沙汰」ではないのでしょうか。人類社会を消滅させる道具を持ち続けることは「狂気の沙汰」ではないのでしょうか。「死神」に命運を任せることは「狂気の沙汰」ではないのでしょうか。私は、仮定の「狂気の沙汰」よりも現実の「狂気の沙汰」の解消が先だと思うのです。
現在、日本では、中国、北朝鮮、ロシアを名指しして「厳しい安全保障環境」が言われています。彼らが日本に攻撃を仕掛けるかもしれないので「抑止力」と「対処力」が必要だとして、自衛隊と米軍の一体化がすすめられ、国力の全てが防衛力の強化に向けられ、「拡大核抑止」が強化されているのです。日本版「先軍思想」に基づいて現代版「国民総動員体制」が作られつつあるのです。その姿勢が、それらの国の「抑止力」や「対処力」を更に強化する原因になっているのです。例えば、北朝鮮は核兵器を開発し、核兵器依存を強化しています。それが「安全保障のジレンマ」といわれる現象です。政府は、私たちをより危険な状況に追い込んだのです。
私はそのような核兵器での対立の危険性から解放されたいのです。
それは「かなわぬ夢」なのでしょうか。軍事力に頼る以外の方法はないのでしょうか。例えば、北朝鮮との国交を樹立したり、中国やロシアと、ASEAN諸国がそうしているように、継続的に話し合いをするということはできないのでしょうか。たいていのことは話せばわかるはずです。
かつて、西ヨーロッパでも戦争は絶えませんでした。今、ドイツとフランス、フランスとイギリス、アメリカとスペインとの間で戦争が起きるなどとは誰も考えていないでしょう。それは信頼関係が醸成できたからです。戦争をなくすことは可能なのです。それは、ASEAN諸国でも同様です。この地域では対話と交流が日常的に行われているようです(※21)。
「諸国民の公正と信義」に基礎を置き信頼関係を形成することは、単に必要だというだけではなく、可能なのです。殺し合いで決着をつけるより、ずっと平和的なのです。人間には理性も言葉もあるのです。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼しての生存と安全の保持」は、必要というだけではなく可能な選択なのです。
◆「戦争前夜」の中で
今、日本は「戦争前夜」といわれる状況になっています。沖縄から本土への住民の避難計画が策定されようとしています。沖縄が戦場になることが想定されているのです。既に「国民保護計画」は策定されていますし、その中には核攻撃があった場合も想定されているのです。武力衝突の準備が着々と進められているのです。再び政府の行為によって戦争の惨禍が引き起こされるかもしれないのです。
私たちは、今、このような現実の中に置かれているのです。
「核兵器も戦争もない世界」をもとめる私たちは、このような現実を転換しなければならないのです。
けれども、いたずらに悲観的になることはありません。核兵器に依存する勢力は存在していますが、核兵器禁止条約は発効しているのです。また、日本国憲法も存在しているのです。私たちには強い味方が付いているのです。
そして、核兵器はピーク時の7万発から減少しているのです。紆余曲折はありますが「核兵器のない世界」への前進は確認できるのです。
最後に確認しておきたいことは、私たちは、見ず知らずの人との殺し合いに駆り立てられるよりも恐怖と欠乏から免れて平和のうちに生活する方が好きだということです。私たちは平和を愛しているということです。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持する」ということは、決して「狂気の沙汰」などではなく、私たちが生き残る、もっとも確かな唯一の方法なのです。
(2025年3月30日記)
- 2024年1月時点、広島県HP
- 1959年6月19日、沖縄の米軍基地で、ナイキミサイルの誤発射事故が起きている。松岡哲平著『沖縄と核』(新潮社、2019年)
- 2025年1月31日 · 米国の科学誌「Bulletin of the Atomic Scientists(ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ、原子力科学者会報)」は1月28日、世界がどれほど破滅の危機に近づいているかを真夜中までの残り時間で表す「終末時計(Doomsday Clock)」の2025年版を発表した。1947年以降最短とされている。
- 拙著『迫りくる核戦争の危機と私たち』(あけび書房、2022年)
- オバマ米国大統領は2016年5月27日の広島で「71 年前の明るい雲ひとつない朝、死が空から降り立ち、世界は変えられた。」(Seventy-one years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed.)と演説している。
- 『軍事研究』電子版14巻1号、2025年3月。
- なぜ、この論稿に着目するかというと、バーナード・ブロディーは「核抑止論」の誕生に関わっている人だからである。浦田賢治『核抑止の理論―誕生・現状・批判』(浦田賢治編著『核抑止の理論』日本評論社、2011年所収)は、彼の著作を学者による「核抑止理論の誕生」の最初としている。
- 外務省には軍縮軍備管理課はあるけれど核廃絶課はない。
- Bernard Brodie, “Implications for Military Policy,” Bernard Brodie, ed., The Absolute Weapon:Atomic Power and World Order, Harcourt, Brace & Company, 1946, p. 76.
- 先の浦田論稿は1959年のブロディーの著作「ミサイル時代の戦略」を上げているけれど、戸崎論稿は1946年の論稿の引用である。ブロディーは核抑止理論の「元祖」といえるであろう。
- 2025年3月30日、日米防衛相会談で「両氏は中国による東シナ海などでの力や威圧による一方的な現状変更の試みに反対するとともに、日米同盟の抑止力と対処力を一層強化していく必要があるという認識で一致」と報道されている。
- 服部学監訳『国連事務総長報告・核兵器の包括的研究』(連合出版、1982年)
- チャーチルの1955年、イギリス下院での発言。アマルティア・セン著・東郷えりか訳『人間の安全保障』(集英社新書、2006年)による。
- ジョセフ・ロートブラットなど編著・小沼通二他監訳『核兵器のない世界へ』(かもがわ出版、1995年)
- ハンス・モーゲンソー著・現代平和研究会訳『国際政治』(福村出版、1998年)
- 中立国とは交戦国からの侵攻や攻撃を受けない代わりに、交戦国のいずれにも便宜を与えてはならないとする立場。
- ジュネーブ条約第1議定書 第55条1項「戦闘においては、自然環境を広範、長期的かつ深刻な損害から保護するために注意を払う。その保護には、自然環境に対してそのような損害を与え、それにより住民の健康又は生存を害することを目的とする又は害することが予測される戦闘の方法及び手段の使用の禁止を含む。」など
- 私は、この報告は核抑止論についての体系的かつ根本的批判であると評価している。前掲拙著『迫りくる核戦争の危機と私たち』(あけび書房、2022年)でも紹介している。
- この宣言は「たとえ水爆を使用しないというどんな協定が平時に結ばれていたとしても、戦時にはそんな協定はもはや拘束とは考えられず、戦争が起こるやいなや双方とも水爆の製造にとりかかるであろう。なぜなら、もし一方がそれを製造して他方が製造しないとすれば、それを製造した側はかならず勝利するにちがいないからである。」としている。
- 憲法学者芦部信喜氏は、憲法9条について「比類のない徹底した戦争否定の態度」としている(『憲法』岩波書店)。前掲拙著『迫りくる核戦争の危機と私たち』でも触れている。
- 日本共産党の志位和夫氏は「域内で年間1000回にも及ぶ会合を開くなど、徹底した粘り強い対話の努力を積み重ねることで、この地域を『分断と敵対』から『平和と協力』の地域へと大きく変えてきました。」としている(2022年1月4日「党旗びらき」でのあいさつ)。